
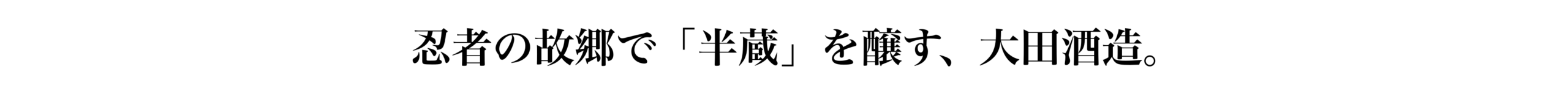

四方を豊かな山々に囲まれた伊賀盆地は忍者の故郷としても知られている。忍者の代表格といえば、徳川家康に仕えた服部半蔵が有名である。日本史の大事件として語り継がれる本能寺の変の際には、家康の三大危機の一つに数えられている堺から三河へ逃げる「伊賀越」を助けたことや、伊賀同心を率いて江戸の治安維持に貢献した功績が称えられて、現在でも「半蔵門」という名前の門が東京に残されているほどだ。

伊賀の偉人とされる服部半蔵から名前をとった銘柄が三重県伊賀市に存在する。創業1892年の大田酒造の代表銘柄として「半蔵」は今日まで大切に引き継がれてきた。服部半蔵の名を冠した銘柄は伊賀の風土を表現する酒として、原料米には伊賀盆地で栽培された酒米である「神の穂」や「山田錦」「うこん錦」を使用して酒造りを行っている。

また、仕込み水には四方の山々から流れ出た軟水の伏流水を用いながら、三重県酵母の「MK-1」や「MK-3」を使用することで、適度な香味がありながらも、伊賀牛などの地域の食材との相性の良い調和のとれた酒質を追求している。

大田酒造の「半蔵」は、2016年「G7伊勢志摩サミット」乾杯酒にも採用されたことでも大きな話題となった。その後も「三重県知事賞」や「ワイングラスでおいしい日本酒アワード」を受賞したことで、国内外で高い評価を受ける酒蔵へと成長を遂げた。

以前までは「東海白鷺」という銘柄の酒を造っていたのだが、1996年より、「半蔵」の生みの親である3代目蔵元、故、大田良一氏が忍者の故郷である土地柄を前面に押し出し、少量・高品質の酒造りで県外への新規開拓を目指した。その後2007年初めて海外のプロモーションに参加。その甲斐もあって、香港に輸出が始まり、現在では全体の製造量の約1割が海外へと輸出されている。徐々に製造石数も増やしており、今後も600石からの増産も計画中だ。

大田酒造の杜氏である大田有輝氏は昔ながらの酒蔵のなかで、寒さの厳しい季節に低温発酵での丁寧な酒造りを行っている。東京農業大学短期大学部を卒業後すぐに広島県の酒類総合研究所や三重県鈴鹿市で「作」を醸す、清水清三郎商店で研鑽を積んだ。杜氏に就任したのは2019年からのことで、若干25歳の若さで現場を統括する立場を任された。

現在は若手メンバーが一丸となって更なる酒質の向上を目指しているそうで、数年前からは大田有輝氏の弟も酒蔵に入って酒造りの現場を兄弟で牽引する。これからも家業の強みを活かしながら、「半蔵」を忍者の故郷から魅力を発信して、世界へと飛び越えていけるように挑戦を続けていく。
文:宍戸涼太郎
写真:石井叡
編集:宍戸涼太郎

