
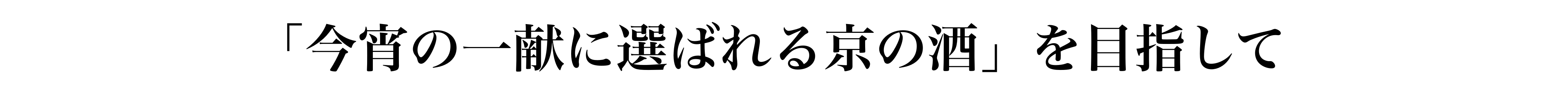

京都市伏見区に蔵を構える松山酒造。代表銘柄の「十石」は、かつて伏見の水運を担った十石舟にちなんで名付けられました。京の玄関口として繁栄した伏見の地で河川での交通・運送の要であった小型舟や十石舟。十石舟は現在でいう、2tトラックのような存在。京都の商流や人流を支えてきた京都の象徴的な暮らしの風景でした。そんな京都の暮らしに馴染み、京都を訪ねてくる人々にも選ばれるような銘柄にしたいという想いから「十石」と命名されました。そして、新しく生まれ変わった酒蔵としても注目を集めており、京都観光での食事から日常の食卓まで飽きのこない日本酒を醸しています。

松山酒造の銘柄「十石」を造るときに使用される素材は全て京都産にこだわっています。酒造りに欠かせない水。伏見の水である「伏水」の硬度は60㎎/L前後の中硬水といわれており、バランスに優れた地下水。京都盆地の地下は水甕のようになっているそうで、その水量は琵琶湖の水量に匹敵するともいわれています。京都市自体が大きなダムというイメージで、周辺の山々から大きな水脈を通して大量の水が流入しているようです。京都市は古くから「水の都」と呼ばれ、食文化や様々な産業が発展を遂げてきました。京都の名産品である湯葉や豆腐、わらび餅などが有名になったことも良質な水が影響しているそうです。そして、京都市は日本三大酒処として多くの酒蔵が軒を連ねています。そのほかにも京都府内には大手ビール工場もあることからも良質な水があることがわかります。この伏水を松山酒造も最大の強みとして活かし、酒造りを行っていく考えです。

また、松山酒造では京都産酒造好適米「祝」を使用して酒造りを行っています。この酒米は京都の酒造組合が管理しており、京都の酒蔵にしか卸されない貴重な品種です。主に京丹後や福知山、与謝野町など京都の北部で栽培され、伏見で酒造りによく使用されています。「祝」は1992年に生産が復活した「幻の酒米」として知られていて、過去に2度も栽培が中止されている品種です。背が高くて倒伏しやすいことや実入りが薄くて収量が見込めないことが中断の理由として挙げられます。醸造面においても「祝」は心白が大きすぎることで精米中に割れやすく、原料処理が難しいという課題もあったそうです。ただ、京都の酒蔵として京都の酒米を大切にしていきたいとの想いや、伏見の水との相性の良さから松山酒造では「祝」のみを原料米として使用しています。そして、「祝」は豊潤な味わいと柔らかな芳香を特徴とする酒に仕上がる傾向にあるようです。松山酒造ではアルコール発酵を促す酵母菌に、京都市産業技術研究所が独自に開発してきた「京都酵母」を使用しています。現在、5種類の京都酵母が存在していますが、松山酒造では「京の琴」という「京都酵母」を採用。青リンゴのような香りをつくるのが特徴の酵母といわれており、非常にバランスに優れた酵母として知られています。そして「京都酵母」の香りは穏やかで、協会酵母の中では特に「協会7号酵母」に似ており、そこに少しだけカプロン酸エチルを加えたようなイメージだといわれています。飲んでくれた人に対して印象を残せるようにと香りを少しだけ出すことに決めただからだそうです。また、「種もやし」と呼ばれる麹菌には京都で創業300年余りも続く「菱六もやし」の種もやしを使用することで、京の発酵文化の歴史を発信していきたいと考えています。

松山酒造の創業は1923年で、三重県名張市で立ち上がりました。1958年には月桂冠グループの傘下に加入して、翌年からは京都市伏見区に酒蔵を移転して酒造りを行ってきました。かつては但馬杜氏や越前杜氏が冬季に酒造りを行う体制で、最盛期には年間で約5000石(900キロリットル)を製造し、他社酒造メーカーに未納税移出するための普通酒を造っていました。しかしながら、近年は需要の低下もあって徐々に製造石数が減少している状況でした。そして、遂には新型コロナウイルスの流行や設備の老朽化などを理由として2021酒造年度からの生産を休止することになりました。社内会議では廃業という方向性も現実味を帯びていました。松山酒造は住宅地にあるので、駐車場にするという案もでていたそうです。

松山酒造が繋いできた創業から100年の歴史や門前を流れる濠川の風情、東堺町の歴史深さなどを鑑みた結果、吟醸蔵へのモデルチェンジと新たな経営方針で再出発を図ることになりました。しかし、当時の松山酒造は他社酒造メーカーへの未納税移出の普通酒を造っていたので、吟醸酒を造る環境が全くない状況でした。そのようなことから、醸造を任せられる人材が必要ということになり、月桂冠で醸造責任者を務めていた経験の豊富な高垣幸男氏が杜氏として再建を任されることとなりました。高垣杜氏は、大手の蔵とはまた違う酒造りに魅力を感じて挑戦を決意したそうです。「これが京都の酒だと誇れるような酒を造り、松山酒造を次の世代に引き継いでいく責任を果たしたい」と抱負を語られていました。現在、松山酒造は高垣杜氏と営業担当の酒井美里氏の2人体制で酒蔵を運営しています。事業を安定させ、後々は蔵人を増やせたらと考えているようです。そして、2023年春に休眠蔵は復活を遂げました。京都の素材を詰め込んだ酒造りを基本方針に据えて、最盛期の100分の1程度の石数である年間製造50石程度の少量生産の体制での再出発でした。初年度は工程や手順を確立することを目指した酒造りだったので、製造量は50石程度にとどまりましたが、今酒造年度で150石の製造を計画しているそうです。そして、今年の酒造りは高垣杜氏が基本的には1人で対応したそうです。そして、蔵の経営方針としては「量を追い求めるというよりは丁寧に販売し、価値を分かってもらうことを優先したい」と酒井氏は話してくれました。特定名称酒に特化し、小規模で高品質の酒を目指すことで、日本の文化や京都の歴史に興味のある観光客にも伏見の酒文化を発信したいと考えているそうです。

高垣杜氏は元月桂冠大手二号蔵の製造責任者やアメリカの「GEKKEIKAN SAKE INC.」での勤務経験のある1966年生まれの57歳で、「定年までの数年間を大手蔵では出来ない酒造りに向き合い、十石という銘柄で有終の美を飾りたい」という想いから杜氏の役割を引き受けたそうです。そして、京都には古都としての集積文化が古くから根付いており、他県から良質な物資を取り寄せることが文化として定着していることに酒処の酒蔵として危機感を抱いていたそうです。現在、京都市内の飲食店では京都以外の近畿の酒や東北の酒が並べられていることも多く、伏見の酒を主力銘柄として取り扱っている飲食店が減少しているそうです。だからこそ、観光で京都を訪ねてきた人々に「十石」を飲んでもらいたいと考えています。そのため、松山酒造では京都の素材だけで醸された伏見の酒にこだわることで、京都市民が誇りに思う酒、京都を訪ねてきた人が京都を感じられる酒を目指していくそうです。そして、京の心意気が詰め込められた「十石」は薫風のように爽やかに、まるで川面を滑っているかのように颯爽と伏見の新たな歴史を刻んでゆきます。
文:宍戸涼太郎
写真:石井叡
編集:宍戸涼太郎