
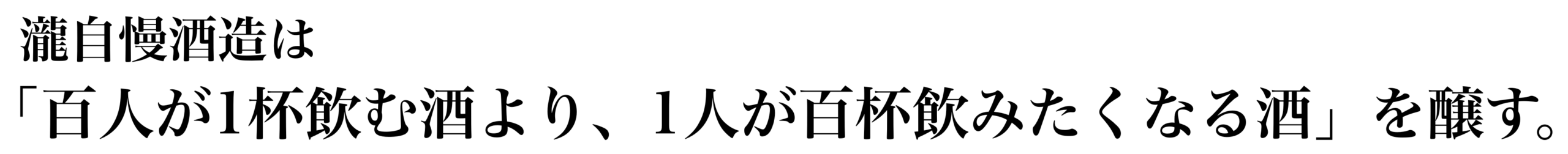

古くから水稲栽培が盛んな地域である伊賀上野盆地には「ついつい杯が進んでしまう酒」を造る酒蔵がある。「平成の名水百選」や「日本の滝百選」にも選出された赤目四十八滝の水は青く澄み渡っており、美しい自然の中の渓谷にはオオサンショウウオが生息する。また、山岳信仰の聖地としても知られており、多くの修験者や伊賀忍者が修行を積んだとされている。

そのような自然の恩恵を存分に受けられる場所で「瀧自慢」を醸す、瀧自慢酒造は滝の伏流水が持つ、仕込み水の柔らかさから、飲み飽きせずに杯を重ねたくなる優しい飲み心地を追求する。地元で収獲された「山田錦」や「神の穂」と呼ばれる、三重県の酒米を使用しながら、三重県清酒酵母の「MK-1」「MK-3」を投入のタイミングを見計らいながら、定番商品である「瀧自慢 辛口純米 滝水流(はやせ)」を造る。そして、この日本酒は「伊勢志摩サミット晩餐会」で食中酒にも採用されたことで一躍注目を浴びた。

それまでは県内の酒販店での流通が中心であったのだが、各国の首脳たちが日本酒を飲んでいる場面が報道されるや否や、瀧自慢酒造をはじめとする三重県の地酒に全国の酒販店が興味を抱いたことで、現在も製造数量600石にあたる約50%が県外に出荷されている。5代目蔵元候補であり、杜氏の杉本龍哉氏は「伊勢志摩サミットの開催が三重県の地酒のイメージ向上に繋がった」と当時を振り返る。

瀧自慢酒造の創業は1868年で、当時は滝川酒造として立ち上がった。初代の杉本杉松は、この土地で酒造りを行っていた人物から経営権を譲渡してもらうかたちで、現在の杉本家が引き継ぎ、滝本酒造という名前で生まれ変わったのが始まりである。戦時中には休造を余儀なくされたのだが、1956年に3代目蔵元の杉本和三が酒造りを復活させた。

それから、4代目蔵元の杉本隆司氏が自ら杜氏となり、滝川の醸造試験センターで学んだ知識と自らの感覚を頼りにしながら、未納税移出の酒を造る経営から脱却を図り、自らの銘柄を立ち上げる方向性へと変革を行った。小さなタンクでの仕込みに切り替えて、温度管理や清掃を徹底することで酒質の向上を図った。その結果、「瀧自慢」は透明感のある食中酒として次第に認知されるようになった。

現在は、5代目蔵元候補で杜氏の杉本龍哉氏が東京農業大学醸造学科や東京の酒販店での修行を終えて戻ってきた。今年で家業を継いで8年目となる。最近になってようやく酒造りのことがわかるようになってきたという。父親が生み出した「瀧自慢」という銘柄を心から美味しいと思っているからこそ、自分は杜氏として「社長が積んできた石を崩すことなく、自分も石を積み重ねていきたい」と意気込みを語る。

そのなかで、将来的には自分の独自色もどこかで表現できたらと思いを巡らせているそうだ。5代目蔵元候補で杜氏の杉本龍哉氏は、これからも試行錯誤を繰り返しながら、地元を明るく照らす存在として「瀧自慢」の酒造りを追求していく。
文:宍戸涼太郎
写真:石井叡
編集:宍戸涼太郎







